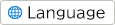古物営業許可申請等の手続き(必読)
新規に古物営業を始めるには、公安委員会の「許可」が必要!!
次のような「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の「許可」が必要になります。
「許可制」になっている理由
古物の売買等は、その営業の性質上、盗難品等の犯罪被害品が混入することも多く、これを放置すれば、古物営業が盗難品の流通の場となるおそれがあることから、これを防止するために「許可制」となっています。
(一定の欠格要件に該当する者については、許可が取得できないこととなっています。)
「古物」とは何?
古物営業法にいう「古物」とは、次のものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「古物」は、古物営業法施行規則(第2条)により、次の13品目に区分されています。
| 13品目の区分 | 例示品目 | |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
|
2 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 4 | 自動車 | その部分品を含みます。 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
| 6 | 自転車類 | その部分品を含みます。 |
|
7 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、計算機、フャクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
|
10 |
道具類 | 家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 12 | 書籍 | |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物営業の許可を受けられない場合(古物営業法第4条)【欠格事由】
次に該当する方は、許可が受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(※注)を犯して罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過したもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の日及び場所が公示された日から取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
(※注)「一定の犯罪」とは
- 古物営業法第31条に規定する罪
- 刑法に規定する窃盗(刑法第235条)、背任(刑法第247条)、遺失物等横領(刑法第254条)、盗品等の運搬等に該当する罪(刑法第256条第2項)
新規の許可申請に関して
必要な書類(添付書類等)
1 「許可申請書」(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)
許可申請書等の様式及び記載例はこちらを参考にしてください。こちらです。
2 添付書類
| 個人許可申請 | 法人許可申請 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 法人の登記事項証明書 | × | ○ |
| 2 |
法人の定款 (現行定款) (※注1) |
× |
○ |
| 3 |
住民票の写し (※注2) |
○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 4 |
市町長の証明書【身分証明書】 (※注3) |
○ 同上 |
○ 同上 |
|
5 |
略歴書 (最近5年間) (※注4) |
○ 同上 |
○ 同上 |
|
6 |
誓約書
(※注5) |
○ 同上 |
○ 同上 |
| 7 |
営業所の見取図等 (※注6) |
△(必要に応じ) | △(必要に応じ) |
| 8 | 営業所の使用承諾書
(※注7) |
△自己所有以外(必要に応じ) |
|
| 9 |
URL疎明資料 【※URL使用時のみ添付】 |
URLを使用する権限のあることを疎明する資料 (当該URLの割当通知又はWHOISにてドメイン検索を行った結果画面をプリントしたもの等) |
|
- 住民票の写し、身分証明書等公務所発行の書類など、いずれも発行、作成日付が申請日から3カ月以内のもの
- 各書類とも、本通を「1通」提出
行政書士等第三者に申請を依頼する場合には、「委任状」が必要です。
前記添付書類のほか、その他の書類等が必要な場合もあります。
前記「添付書類の一覧表」の注意点(※注1~7)は、次のとおりです。
※注1【法人の定款】
- 法人の定款はコピーで可ですが、添付する定款の末尾に、「この定款は、現行のものと相違ありません。記載年月日、法人名、代表者名」を記載してください。
- 「目的」など登記事項証明書との相違があれば「議事録」の提出を合わせてお願いします。
※注2【住民票の写し】
- 住民票の写しは、「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたものです。
- また、「個人番号」は、”記載がないもの” をお願いします。
※注3【市町長の証明書】
- 身分証明書は、本籍地の市町村が発行する「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記を受けていない、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと」を証明するものです。
- 外国人の方は、発行されませんので「在留カードの写し」を提出してください。
※注4【略歴書】
- 過去5年間の経歴について空白の期間がないように記載してください。
※注5【誓約書】
- 誓約書の署名欄には、必ず、本人の署名をお願いします。(代筆不可)
※注6【営業所の見取図等】
- 申請を受ければ、適切な営業が可能か事前に警察官または警察職員が調査に伺います。営業所の所在地がわかりづらい場合は添付してください。
※注7【営業所の使用権原を明らかにする書類(使用承諾書)】
- 過去、警察官等が調査の際、貸主との間でトラブルが発生しています。必要に応じてご使用ください。
3 手数料
- 19,000円(証紙)
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
許可申請等の窓口
営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課又は生活安全・刑事課)
※事前に各警察署の窓口まで電話連絡をお願いします。
(窓口担当者等が不在の場合もありますので、ご注意ください。)
※県内に2以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署へお問い合わせください。
許可証の交付
申請を提出した警察署から許可・不許可の連絡をします。
新規許可申請の標準処理期間は、「概ね40日」です。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替えなどがあった場合は、遅れる場合があります。
◆その他の手続き
1 変更届出等
- 古物商等は、営業内容等に変更があった場合には、「変更届出書」を提出し、変更内容が許可証の記載事項に関する場合には、許可証の書換えを受けなければなりません。
- また、許可証を亡失等した場合は「再交付申請」、古物営業を廃止した場合などは「返納理由書」の届出などの手続きが必要になります。
各種申請・届出書の様式及び記載例はこちらをご覧ください。こちらです。
2 手数料
- 許可証の書換申請 1,500円(証紙)
- 許可証の再交付申請 1,300円(証紙)
営業開始後の手続きは、基本的には、許可証の交付を受けた警察署になります。
※手続きの詳細については、許可証の交付を受けた警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課に確認してください。